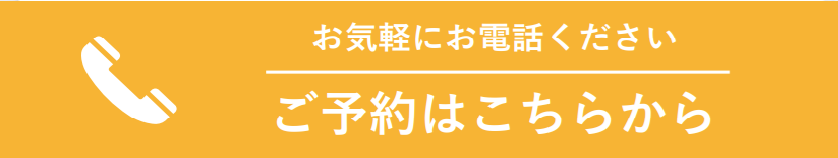姿勢の崩れが体調不良に!?食べる時の正しい姿勢

近年、私たちの生活様式は大きく変わり、それに伴って「食事のかたち」も少しずつ変化しています。
こうした背景の中で、特に注目したいのが「食事中の姿勢」と「食べ物の噛み方」です。
これまでは、ひとりで食べる「孤食」は心身の健康や社会性の観点から好ましくないとされてきましたが、現在で周囲と距離を保ちつつ、食べることに集中できる時とも捉えられるようになってきました。
姿勢の崩れは体の不調を招くことも

会話のない食事スタイルは、スマートフォンやパソコンを見ながらの“ながら食べ”や、猫背で前かがみの姿勢などを助長しやすくなります。その結果、あまり噛まずに早食いするといった習慣が無意識のうちに身についてしまっているかもしれません。
このような姿勢の乱れは、首や肩のこり、頭痛を引き起こすだけでなく、咀嚼不全や消化不良の原因にもなります。
特に近年話題の「スマホ首(ストレートネック症候群)」は、首・肩の筋肉の緊張だけでなく、咀嚼や飲み込みに関わる筋肉群にも悪影響を及ぼします。
さらに下を向いた姿勢が続くと、唾液腺が圧迫されて唾液の分泌が減少し、噛み合わせのズレや左右バランスの乱れが生じ、顎関節の不調を引き起こすこともあります。
このように、姿勢の崩れから連鎖的に身体へ負担がかかることもあるのです。
正しい姿勢を意識して「食べること」に向き合う

こうした環境の変化は、裏を返せば「食べることに集中できるチャンス」とも言えます。
食事中の姿勢を見直すことで、咀嚼機能や消化機能の向上、顎関節や筋肉への負担軽減につながります。
ここでいう「正しい姿勢」とは、「美味しく食べられて、健康な咀嚼機能と消化機能が保たれる姿勢」のこと。以下のポイントを意識してみましょう。
食べるときに意識したい「正しい姿勢」4つのポイント
1. 背筋をまっすぐに伸ばす
猫背で前かがみになると、顎の筋肉が動かしづらくなり、噛み合わせが前にずれて「前噛み」になりがちです。
背筋をしっかり伸ばして体幹を安定させると、顎まわりの筋肉がスムーズに働き、奥歯でしっかり咀嚼できるようになります。
2. 顎を上げすぎない
首を突き出した姿勢や顎が上がった状態では、喉頭と気道が直線に近くなり、誤嚥のリスクが高まります。
顎を引いて自然な角度を保つことで、喉頭と気道の間に適切な角度が生まれ、誤嚥を防ぎやすくなります。
3. 足の裏をしっかり床につける
食事中に足を組んだり、足を前に投げ出したり、足裏が浮いている状態では、飲み込みが難しくなることがあります。
実際に寝たきりの方でも、足裏がしっかり接地するように工夫すると嚥下がスムーズになるという研究報告もあります(川邊研次『顎関節症は姿勢と咬合と筋力の問題』2011年)。
介護現場などでは、車いすを利用する方が食事をとる際、足元に台を置いて姿勢を安定させることも一般的です。
4. “ながら食べ”を避ける
スマートフォンやパソコンを見ながらの“ながら食べ”は、どうしても姿勢が崩れやすく、1~3の基本的なポイントを守れなくなってしまいます。
せっかく集中して食べられる環境が整っている今だからこそ、目の前の食事に向き合い、よく噛み、味わって食べる時間を大切にしましょう。
また、こうして「よく噛もう」と意識したときに、「噛みにくい」「顎が疲れる」「痛みがある」などの不調に気づく場合もあります。
それは、これまで気づかずにいたお口の異常が“正しい姿勢と咀嚼”によって表面化したサインかもしれません。
少しでも気になることがあれば、ぜひ歯科医院でご相談ください。お口のケアは、全身の健康維持と深く関係しています。日々の食事から、健康づくりをはじめてみましょう。
三重県津市でお口のお悩み・入れ歯相談なら田中歯科
「お口の健康は、心と体の調律へとつながる。」と田中歯科は考えております。皆さまの健康を根本から支える歯科医療を提供し、お口の健康を整えることが、心の調律にもつながる。
このように「病は気からを科学する」それが私たちのミッションです。

医院名
田中歯科
院長
田中伸子
所属学会・資格情報
・日本抗加齢医学会(JAAM) 専門医
・日本アンチエイジング歯科学会(JSDA) 認定医
・JSDA ペリオフードコーディネーター
・JSDA サプリメントアドバイザー
・JSDA ビューティーアドバイザー
・日本歯周病学会 正会員
住所
三重県津市大門15-16
アクセス
バス:津駅前より京口立町で下車し徒歩7分 お車:津駅より車で約5分(専用駐車場あり)
ご予約はこちら
059-228-6444